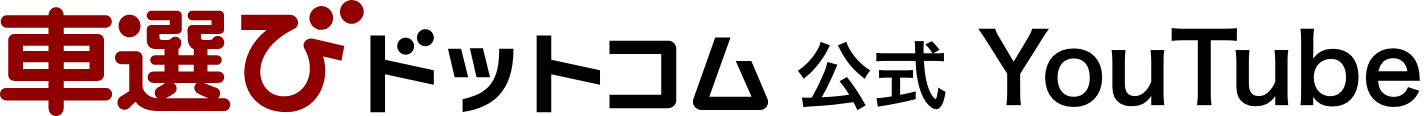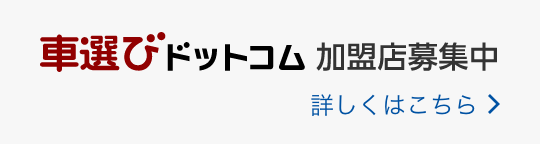2台目の自動車保険に使えるセカンドカー割引とは

子育て世帯を中心に、自動車を2台持ちするケースがあります。通勤や子どもの送迎などに必要なため夫婦で1台ずつ所持するなど、ライフスタイルに合わせて車が2台あるほうが便利だからです。
車を2台所持すると維持費なども2倍になりますが、2台目の自動車保険には割引が適用される場合があります。
そこで今回は2台目の自動車保険に使用できるセカンドカー割引について、適用条件や注意点を詳しく解説します。
- Chapter
- セカンドカー割引とは?
- セカンドカー割引が適用される条件
- セカンドカー割引の注意点
- まとめ
セカンドカー割引とは?

自動車保険の「セカンドカー割引」とは、2台目の保険料がお得になる割引制度です。セカンドカー割引を利用することで、「等級」が通常よりも上からスタートすることができます。
等級とは

自動車保険には等級があり、等級によって割引率が異なります。等級は1等級から20等級まであって、等級の数字の大きなものほど割引率が高くなります。
等級は無事故であれば上がりますが、事故を起こすと下がってしまいます。
事故の内容で等級の下がり方が定められており、事故を起こした場合は、等級は3つ下がるのが基本です(3等級ダウン事故)。
しかし中には、1つしか等級が下がらない事故(1等級ダウン事故)も存在します。車が盗難にあったり、自然災害が原因となったりして保険金が支払われた場合は、1等級ダウン事故と認定されます。
自分に過失が無ければ、等級は1つしか下がらないと覚えておきましょう。
等級が下がると保険料が高くなってしまうので要注意です。
セカンドカー割引を利用した場合の等級
等級は6等級からスタートするのが原則ですが、セカンドカー割引を適用することによって2台目は一つ上の等級である7等級からスタートすることができます。
そのため、車を2台持ちしたい人はセカンドカー割引を利用することで保険料を安く抑えるのが最適です。
またセカンドカー割引は2台が同じ保険会社でなくても適用されます。ただし適用のためには条件がありますので事前に確認する必要があります。
セカンドカー割引が適用される条件

2台目の車には自動車保険のセカンドカー割引を活用するべきですが、セカンドカー割引の適用には条件があります。
損害保険会社によって細かい条件は異なりますが、基本的に1台目の等級が11等級以上なくてはいけません。
セカンドカー割引は、1台目と2台目が異なる保険会社であっても構いませんが、その場合でも1台目が11等級以上であることが必須になります。
また1台目の保有者は個人であることもセカンドカー割引の条件です。さらに2台目の保険加入が新規であることも条件になります。
セカンドカーは新車でなければいけないの?
セカンドカー割引を活用する場合には全くの新規で保険に加入することがポイントになりますが、車は新車でなくても構いません。
車を他人から譲渡された場合でも、前の人の保険を解約し新規で加入すればセカンドカー割引を適用されます。
ただし、2台目の保有者については誰にでもセカンドカー割引が適用される訳ではなく、1台目の保有者の配偶者や同居している家族に限られますのでこちらも注意が必要です。
また任意保険にも加入していることが条件です。
【セカンドカー割引の適用条件まとめ】
・1台目の車の等級は11等級以上であること
・1台目の保有者は個人であること
・2台目の保険の加入が新規であること
・2台目の保有者は、1台目の保有者の配偶者や同居している家族であること
セカンドカー割引の注意点

セカンドカー割引を利用する際の注意点は、適用条件を満たしているかを確認することです。
自動車保険の中でもセカンドカー割引の適用条件はハードルが高くありませんが、事前にクリアしているかチェックしましょう。
また、自動車保険の補償内容が重複していないか確認することも重要です。自動車保険の中には契約者本人だけではなく、配偶者や家族も補償されるものがあるからです。
重複する補償がある場合には、2台目で同じ補償をかける必要はないので、その分のコストが無駄になってしまいます。
このような場合には契約内容を見直すと保険料をおさえることにもつながりますので、しっかりと確認しましょう。
また、セカンドカー割引は2台とも同じ保険会社である必要はありませんが、同じ保険会社を利用するとセカンドカー割引がさらにお得になることもありますので必ず確認した上で加入しましょう。
まとめ
- 2台目に適用される自動車保険にはセカンドカー割引があります。
- セカンドカー割引は通常であれば6等級から始まる等級を、7等級からスタートすることができます。その分保険料を安くすることができます。
- セカンドカー割引には適用条件があります。1台目が11等級以上であることや、1台目の保有者の配偶者または同居している家族であることなどです。