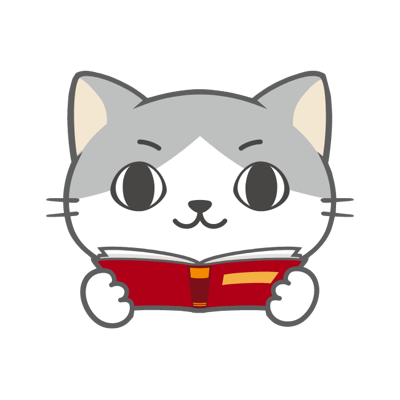親名義・他人名義の場合の車売却【代理でも手続きはできる?】
基本的には車の売却を検討する際には、主に車の所有者本人が手続きを進めます。しかし、親や友人などに頼まれて代理で売却したいという場合もありますよね。
自分の名義ではなくても車を売ることはできるのかどうか気になっている方もいるかもしれません。
結論から言いますと、親や他人の名義でも代理売却は可能となっています。
しかし、その場合に注意点がいくつかあります。
- 代理売却の場合は必要書類が増える
- ローンが残っている場合は所有権留保解除が必要
これらについて、詳しく説明していきます。
親名義の車を売る場合の必要書類と手続き

①親が健在な場合
親名義の車を譲り受けていて特に名義変更手続きをせずに乗っていて必要がなくなったから売りたいときや、親が高齢になったり障害を負ったりして車に乗らなくなったから売ろうと思ったときなど、親名義の車を代理で売却したいと考えるケースはしばしばあります。
このようなときに親が健在であれば必要書類を整えるだけで特にトラブルなく買取業者に売却することが可能です。
- ・車検証
- ・自賠責保険証明書
- ・自動車納税証明書
- ・リサイクル券
- ・印鑑証明書(親のもの)
- ・譲渡証明書(親の実印が必要)
- ・委任状(親の実印が必要)
- ・自分の印鑑
- ・身分証明書
買取を依頼する際には車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、リサイクル券が常に必要になります。これに加えて印鑑証明書と譲渡証明書も必要になりますが、印鑑証明書については親のものを用意し、譲渡証明書への記入の際には親の実印を使わなければなりません。
また、所有者の実印を押した委任状も用意しなければなりません。委任状については国土交通省から典型的な書式が提供されているので利用すると便利です。親の実印を持ち出せない場合には予め譲渡証明書を国土交通省のホームページから手に入れるなどして作成しておく必要があります。
また、買取手続きの際には自分の印鑑と身分証明書も必要になるので合わせて持参するのが必須です。
一方、親が健在ではない場合には状況がやや異なります。
②認知症など代理人を定める判断力が欠けている場合
認知症になってしまっていると代理人を定める判断力が欠けているため、委任状があっても意味がありません。この場合には原則として成年後見人を立てた上で手続きをする必要があります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てをすると認めてもらうことが可能です。この場合の書類については印鑑証明書も成年後見人のものを用い、実印についても成年後見人のものが必要とされています。
それに加えて成年後見人を証明する書類も用意することで売買契約をすることが可能です。
③親が亡くなっている場合
少し厄介なのが親が亡くなってしまったために売るときです。この場合には所有権を移転しなければなりません。まずは陸運支局で移転登録をした上で自分名義で売却を行わなければならないのが原則です。
移転登録には相続の際に作成した遺産分割協議書と、相続人全員分の印鑑証明書、被相続人との血縁関係がわかる戸籍謄本の用意が求められます。この手続きを行ってしまえば自由に自分の判断で売ることが可能です。
他人名義の車を売る場合の必要書類と手続き
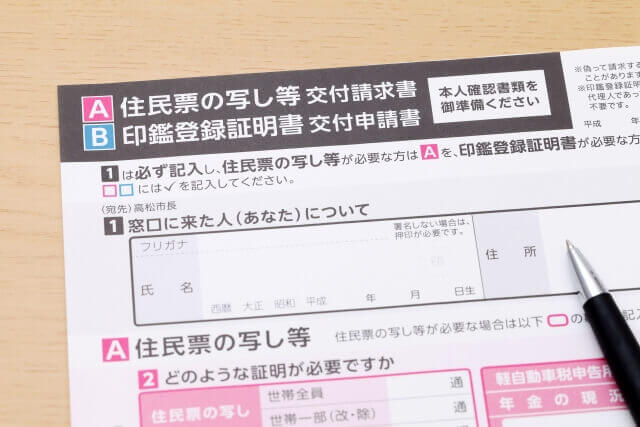
- ・車検証
- ・自賠責保険証明書
- ・自動車納税証明書
- ・リサイクル券
- ・印鑑証明書(所有者のもの)
- ・譲渡証明書(所有者の実印が必要)
- ・委任状(所有者の実印が必要)
- ・自分の印鑑
- ・身分証明書
友人や親戚に頼まれたケースを代表例として他人名義の車を売りたいという場合にも代理人として手続きをすることが可能です。
親名義の場合と必要事項はほとんど同じであり、車の買取業者との手続きの際に必要書類さえ整えられれば問題なく売却できます。
一般的な売却手続きと同様に車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、リサイクル券を用意するのが必須です。そして、印鑑証明書については友人や親戚などの所有者のものを用意し、譲渡証明書にはその人の実印を押してもらえば問題ありません。そして、委任状についても所有者の実印を押したものを用意すれば手続きができます。
①海外に友人や親戚などがいる場合
ただし、一つ気をつけておきたいのが海外に友人や親戚などがいる場合です。所有者の印鑑証明書を用意することができないので手続きに困ってしまいがちですが、この場合には日本大使館で所有者に手続きをしてもらえば問題は解決できます。
サイン証明や捺印証明を発行してもらえるため、それを送ってもらえれば印鑑証明書の代わりに使用できるのです。
②友人や親戚などが認知症/亡くなっていた場合
また、友人や親戚などが認知症になっていたときや亡くなっていたときにも親の場合と同じ手続きを行う必要があります。他人なので自分が成年後見人を立てることを申し立てられず、遺言状がない限りは相続できることもありません。
友人や親戚などの親族の力を借りて申し立てをしてもらった上で委任状などを用意してもらう、相続後に車を譲渡してもらうか委任状などを準備してもらうといったことが必要になります。
ローン会社名義の車を売る場合の必要書類と手続き
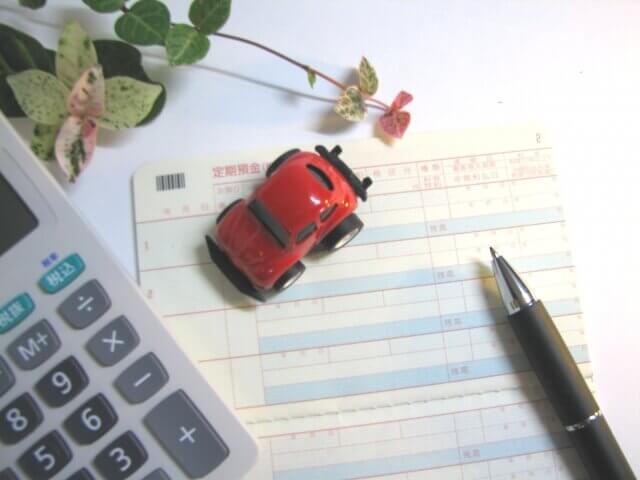
自動車ローンを使って車を購入したときには車の所有者はローン会社になっています。ローンを完済することによって所有者変更を行い、自分の名義の車として利用できるようになるのが原則です。
ローン会社名義になっているときでも車売却を行うことはできます。
所有権留保解除の手続きが必要
ローンが残っているときには所有権留保解除の手続きを行う必要があり、原則としてローンの残債を返済しなければなりません。残債がある限りはローン会社が担保として押さえておかなければならないからであり、相当額の現金を準備するのが需要です。
そして、ローン会社に繰り上げ返済を申し込んで返済すればそれで自分の名義になるので解決されます。もし完済できるほどの予算がないという場合には買取業者に仲介を依頼して手続きを行ってもらのが簡便な方法です。売却価格の一部を使って返済するという形で所有権留保解除を行ってもらえます。
買取金額が残債に満たない場合はローンの組み直しが必要
残債をまかなえるほどの買取金額にならない場合にはローンの組み直しが必要です。買取業者の多くでは残債ローンを提供しているので、それに組み直した上で所有権留保解除を行ってくれます。この際にも必要書類にはあまり大きな違いはなく、ローンに関する一式の書類を用意する必要があるだけです。
他は車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、リサイクル券、自分の印鑑証明書を用意しておけば大丈夫でしょう。
買取業者に依頼すれば委任状や譲渡証明書は用意してもらえるので自分で手配する必要はありません。ローン会社とのやり取りについても任せてしまうことができるので、手続きの上では自分名義の車を売却するときとそれほど大きな違いはないのが特徴です。
ただし、ローンの組み直しをする場合には新たに契約書を交わさなければならなくなります。その重要事項について説明を受けることになり、金利などの内容についてよく理解した上でサインすることが必須です。
身分証明書と印鑑以外に契約に使うものは特にないので、このために何か特別に準備をする必要はありません。
まとめ
- 親や他人の名義でも代理売却は可能
- 代理の場合は必要書類が増えるので注意
- ローンが残っている場合は所有権留保解除が必要
親や他人の名義の車であっても必要書類を用意することができれば代理で車を売却することは可能です。
特に必要になるのが所有者である親や他人の印鑑証明書と実印を押した譲渡証明書や委任状であり、実印を借りられない場合には予め準備した上で売買契約をしに行く必要があります。
ローンが残っている場合にはローン会社が名義人ですが、この場合に売却するには所有権留保解除が必須です。ローンを繰り上げ返済するか残滓を車の売却で得られる現金と残債ローンで充当しなければなりません。
まずは愛車の値段を調べてみよう
愛車を少しでも高く売りたいとお考えの方は、一括査定サイトで愛車の価格を調べるのがおすすめです。
車選びドットコムの一括査定なら、愛車の情報を1回入力するだけで近くにある複数の買取店へ一括で相見積もりできます。 あとは査定額を比較して一番高く売れる店舗で売却するだけ!もちろん、査定額に満足できなければ売却する必要はありません。
愛車の本来の価値を知るためにも、まずは値段を調べてみましょう!
![]() 当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。